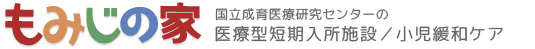なぜ、内多は30年務めたNHKを辞めて、もみじの家のハウスマネージャーに転身したのか?その軌跡をたどった長編自叙伝をお送りします。
【第一章】 NHKアナウンサーが模索した、自分なりの正義
正義の記憶
『義を見てせざるは勇無きなり』(人として行うべき正義と知りながらそれをしないのは、勇気がないのと同じことである。)
私は、この言葉が好きです。いつかはそういう人になれれば良いなと、密かに思っています。しかしながら、「おまえは実行が伴っているのか」と問われると、胸を張ってそうだと言えるわけではありません。
正義の記憶をたどると、話は45年程前にさかのぼります。私は小学生の頃、正義の味方への憧れが非常に強い少年でした。特に、仮面ライダーへの執着は半端ではありませんでした。常に弱い人の味方になり、大勢の敵に対しても単身ひるまずに立ち向かう姿に、すっかりとりこになってしまったのです。テレビの前にくぎ付けになったのは言うまでもなく、学校では来る日も来る日も「仮面ライダーごっこ」(もちろん、私はライダー役です)。おかげで、当時の写真は変身ポーズでキメているものばかりになってしまいました。大人になってから見ると、とても恥ずかしい出来栄えです。“勧善懲悪”という言葉がまだ輝いていた昭和40年代、私はそんな環境の中で、正義とは何かを学んでいったように思います。
でもどういうわけか、中学、高校と進むうちに、正義の感覚は影を潜めていきました。特に大学時代は個人の楽しみのためにほとんどの時間を費やし、授業をサボったり深夜まで遊びほうけたりの毎日。学問への情熱を失い、本を読む気さえ起きませんでした。将来自分が進むべき道を探ろうともせず、誰かのために力になろうという精神は消えうせていたように思います。時代はまさにバブル経済を巻き起こそうという上昇気流が勢力を強め、社会全体が浮かれていました。その気流に乗り損ねた人たちへの視点を、私はまったく持ち合わせていませんでした。昭和という時代がそろそろ終わろうとしていた頃、モラトリアムの私は、なんともお気楽な人生を謳歌していたのです。
尾崎豊の衝撃
音楽は大好きでした。楽器を演奏することはできませんでしたが、熱心にヒット曲を聞いていました。そんなある時、能天気な大学生の私の耳に、あるミュージシャンの歌が強烈なインパクトで飛び込んできました。26歳で亡くなったカリスマ的シンガーソングライター、尾崎豊です。
「大人たちは心を捨てろ捨てろというが、俺はいやなのさ」「夢のために生きてきた俺だけど、シェリー、お前の言うとおり、金か夢かわからない暮らしさ」
学校や社会が抱える不条理や生きることの意味を、メッセージ性のある歌詞と魂から絞り出すような叫びで問いかけるスタイルに、当時の若者の多くが心をわしづかみにされました。私も、繰り返し繰り返し、尾崎豊の世界に浸るようになりました。今思うと、やはりそこには、正義の感覚が宿っていたように思います。仮面ライダーのように、わかりやすい悪物が存在するわけではありません。尾崎豊が立ち向かっているのは、大人や社会という漠然とした対象であり、矛盾をはらんだ規則や既成概念でした。それが「自由」という大切な権利を脅かす悪の存在と感じたからこそ、尾崎豊は牙をむいたのだと思います。久しぶりに正義の感覚を呼び覚まされるような、頭を思い切りひっぱたかれるような、衝撃的な体験でした。ちゃらんぽらんだった20歳の私は、尾崎豊のインパクトを受けて、ようやく真面目に、自分の将来進む道を考えるようになったのです。
ひとり一人の幸せに目を向けた放送を
一時は教師の道を目指したこともありましたが、縁があってNHKのアナウンサーとなり、番組を通じてメッセージを伝えることを仕事にするようになりました。
「放送で社会を良くしたい」「番組で人を幸せにしたい」
放送に携わる者として、若い頃、私はこんなことを夢想しておりました。それは、極めて漠然とした情熱でした。具体的な方法論があったわけではありません。ただ、それまでの歩みを振り返ってみると、自分という人間は、テレビから様々な価値観を吸収し、影響を受け、成長してきたことは明らかです。幼い頃は仮面ライダーの「正義感」や巨人軍・王貞治選手がかっとばすホームランの「絶対的な強さ」に熱狂し、思春期にはドラマで描かれる「人間性の奥深さ」を学び、成人してからはドキュメンタリーが伝える「真実」に胸が躍りました。長い間、テレビから感動や興奮や生き方のヒントを注入されてきた経験が、「自分にも何かできるかもしれない」という妄想を膨らませてしまったようです。
晴れてマスコミの一員となりましたが、困ったことに政治や経済には無関心、事件事故にも興味がわきません。そんな私は自然と、福祉の現場を取材するようになっていきます。今も記憶に残るエピソードを、ご紹介しましょう。
ある日、香川県で行政からの補助を受けて運行されている福祉タクシーが財政難から廃止される方針だという情報が流れてきました。私は早速、福祉タクシーで外出することで社会との接点を保っている車椅子の男性を取材し、男性が地域で孤立せずに暮らすためには福祉タクシーが大切な存在になっていることをリポートしました。そしてしばらくたつと、事態が一変しました。今度は一転して「福祉タクシー存続へ」というニュースが伝えられたのです。取材でお世話になった、車椅子の男性の笑顔が目に浮かぶようでした。これは私にとっても、純粋に嬉しい体験でした。何となく人の役に立てたんじゃないか、困っている人の力になれたんじゃないか、もしかしたら小さな正義を実行できたのかな、そんな気分になった記憶が残っています。
テレビの仕事は放送されたら終わり。苦労して番組を作っても、こちらの思いが100%伝わることは、めったにありません。無力感を感じることも、しばしばです。でも、福祉タクシーの放送で感じた手応えは、私に少し自信をくれました。「大勢の人を幸せにすることはできなくても、ある一人の幸せについて深く考えることが、社会を変えるきっかけになることがある。」そう実感することができたからです。この経験によって、自分の目指す方向は、「誰かが耳を傾けなければ孤立して埋もれてしまう声を、丁寧にすくい上げること」に定まったように思います。「自分は、ひとり一人の幸せに目を向けた放送を目指そう。」マスコミ人となった私にとっての正義がおぼろげながら見えてきた、初任地、四国・高松での出来事でした。
【第二章】 壁を打ち破る番組との出会い
ぼやけていく“正義の輪郭”
NHKの中でキャリアを積むごとに仕事の可能性が広がっていきましたが、その一方で、壁を感じることも増えていきました。自分が正しいと思う方向で番組を提案しても、社会的に議論を二分するような大きなテーマであれば、いくら情熱を持って臨んでも個の力だけでは実現は困難です。社会を良くするためと思って書き上げた企画書も、決定権のある管理職のハンコがなければ、ただの紙屑となります。高い壁を乗り越えられず、自分が夢を描いた放送という世界に限界を感じるようにもなりました。番組を通して表現したかった正義の姿も、輪郭がぼやけていきました。
逆転の発想が常識を変える
そんなある時、仲間の協力もあって提案が通り、20世紀の終わりに番組がひとつ生まれました。それは、自閉症のTさんが川崎市の公務員として働いている姿を記録したドキュメンタリーでした。自閉症の人は一般にこだわりが強く、Tさんも水やトイレが大好きで、子どもの頃は道行く人にホースで水をかけたりして、叱られていました。お母さんは、そのこだわりをやめさせようとしましたが、子どもがパニックを起こしてしまうので、それもできません。
そこで、逆転の発想が生まれます。 「こだわりは人一倍興味が強い証拠。それを生きる力にすれば良い。」 お母さんは、水を存分に使える風呂やトイレの掃除を教えました。Tさんは誰よりもピカピカに掃除ができるようになり、公務員試験にパスした後、川崎の老人ホームで清掃の仕事を続けています。こんな番組でした。
私は番組が放送されること以上に何かを期待していたわけではありませんでしたが、放送後しばらくして、Tさんのお母さんが、ちょっと嬉しい話を聞かせてくれました。 「あの番組ができる前は、自閉症のこだわりは絶対にやめさせるべきだ、というのが世間の常識だったけど、あれ以来、無理矢理やめさせることはなく、その人の個性としてとらえるべきだという認識に変わっていきました。」 お母さんのこの言葉を聞いて、私の心の中には新しい感覚が生まれていました。「放送って、やっぱり捨てたもんじゃないな」
一皮むけた正義の感覚
この番組は、自閉症という、当時はほとんど知られていなかった障がいにスポットを当てたものでした。それを正義と呼べるかどうかはわかりませんが、地味な営みであっても、放送で光を当てることで、それまでの社会の価値観をゆるがすような波紋が広がることもある。そんな手ごたえを感じた経験でした。さらに、その人にとって幸せとはいったい何なのか?ということについて深く考えさせられる体験にもなりました。それは、ひとりよがりに想像するものではなく、当事者の声に耳を傾け、寄り添わない限り、決してわからないものだという明確な答えを、私に与えてくれたのです。
自閉症という言葉には、どうしても「心を閉ざしている」というイメージがつきまといます。取材を始める前は、私にもそんな先入観がありました。ところがTさんに接してみると、心を閉ざすどころか、よく喋る、絵も上手、カラオケも大好きです。コミュニケーションが苦手なだけで、意思疎通ができないわけではありません。挨拶をすれば、誰も真似ができないような大きな声で「おはようございます!」と、ひとつひとつの音をハッキリと正確に発音します。その一途な発声は、自然と周りに微笑みをもたらしていました。
休みの日には、一人でふらっと自転車旅にでかけ、ビールのつまみも自分で器用にササっと料理します。私よりもはるかにアクティブで、生き生きと自立しているようにも思えました。そして気がつくと、Tさんの暮らしぶりや生き様は、私が勝手に抱いていた思い込み(自閉症⇒障がい⇒気の毒⇒不幸)を、あっさりと消し去っていたのです。狭い世界で積み上げただけの自分勝手な常識を、きれいにリセットしてもらったような気分でした。それはすなわち、その人にとって何が幸せかという考え方にも修正を迫る体験となったのです。
「自閉症の息子を抱えると、お母さんは不幸な一生を送ることになるんだろう」こんな決めつけも、何の意味も持たなくなります。一般的な幸せの形とは一味も二味も違いますが、息子が公務員という安定した仕事に就き、地域の支えもあってずっと親子が一緒にいられる。お母さんは今、自閉症の息子と過ごす日々を「幸せな人生」だと感じています。そして息子のTさんについても、「本当に幸せな人生を歩んでいる」と思っています。
私は教えられました。幸せとは極めて個別的なものだから、誰かが幸せか不幸せかを自分勝手に判断することは戒めなければならない。誰かの幸せを支えることが正義だとするならば、それを実行するためには、まず、その人の真の声に耳を傾けようとする姿勢が欠かせない。そうしなければ、何が正義なのかを正しく判断することはできないのです。ヒーロー対悪者という単純な構図でしか理解できなかった子どもの頃の「正義」が、ようやく一皮むけたようでした。Tさんとその家族を通して学んだこの教訓は、今も私の仕事を支える大切な原点となっています。
それから14年たって、私は運命的な番組を担当することになります。
【第三章】「クローズアップ現代」で提起した課題に直接向き合う現場へ
退職、そして転身
運命的な番組とは、“医療的ケアが必要な子どもたちが退院した後、家族の暮らしをどう支えていくのか?”その最前線を追った、クローズアップ現代。まさに、私が新天地に選んだ「もみじの家」の目的とぴったり重なるテーマです。取材を通して私が目にした現実を、プレイバックしてみましょう。
各地の小児病院で満床状態が続くNICU(新生児集中治療室)。小さなカプセルの中で、呼吸管理や栄養注入のためのチューブをつけられた赤ちゃんたちが必死に命をつないでいました。その子たちは、チューブをつけたままの退院を余儀なくされます。次にNICUを必要とする赤ちゃんのため、それはやむを得ないことでした。医療技術が進歩したことで新生児の救命率が向上した反面、濃厚なケアが必要なまま自宅に戻らざるを得ない子供たちが増え続け、退院後も家族には終わりの見えない負担がのしかかります。ケアに追われて落ち着いて寝る時間がなく、神経をすり減らしながら、子どものケアを続けているお母さんたちが全国にいます。「一日一回は『もうだめだ』と思う瞬間があります」そんな切実な母親の言葉にも触れました。まさに、社会や制度から遠ざけられた、埋もれた声を突きつけられた思いでした。退院という言葉は、決して良いイメージだけでなく、その後に背負わなくてはならない、いつ終わるとも知れない過酷な日々の始まりでもあるということを、私は思い知らされたのです。
番組の冒頭のスタジオで、私は、こうコメントしたことを、今でも覚えています。
「今や世界で最も新生児の命を救うと言われる日本ですが、今度は、救った命をどう守っていくかという、新たな宿題を背負っています。」
そのシビアな現実に光を当てたいと、私が直接ロケをした現場の一つが、国立成育医療研究センターだったのです。当時はまだ「もみじの家」ができるという話は欠片も聞こえてきませんでしたが、あの時に築いた人脈によって、今回のハウスマネージャー就任への道が作られたことは間違いありません。取材を通じて交流を深めた関係者から、後日「もみじの家」創設の情報を聞かされ、ハウスマネージャーを担う人材を探していることを知りました。「クローズアップ現代」の放送をすることで、それまでほとんど顧みられることのなかった問題に一筋の光を当てることはできましたが、放送が済んでも、課題は課題として依然大きく横たわっています。自分の中に刻まれた問題意識も、深く沈殿したままです。「もみじの家」は、その重い宿題を軽くできる可能性を秘めた現場として私の目に魅力的に映り、退職、そして転身という大きな決断にいたりました。人のつながりが、突然、私の人生を思わぬ方向に軌道修正していったのです。
まったくの畑違いへの転職に、私の家族や知人・友人たちは一様にビックリしています。かくいう私にとっても、思いがけない大転換ではありましたが、実は根っこの部分ではつながっているのも確かなことです。それは、やはり正義の感覚といえるのだと思います。「もみじの家」は、退院後も医療的ケアが必要なお子さんとご家族が、数日間安心してゆったり過ごしながら、活力を養える環境を提供する施設です。将来的には同じような施設が全国に広がるよう、モデルとなることを目指しています。まさにそれは、苦しんでいるひとり一人を支えながら、社会を変革していこうという試みで、放送を通じて私が取り組んでいた営みと一致するのです。
50歳を目前に一念発起!
そしてもう一つ、私が「もみじの家」に籍を移すことになった要因として、3年前に取得した資格があげられます。それは、社会福祉士という国家資格です。あまり知名度はありませんが、ソーシャルワーカーとも呼ばれる専門職で、福祉施設や病院などで活躍しています。簡単にいうと、支援を必要としている人と、その人をサポートする人材や制度を結び付けることが仕事です。福祉をキーワードに放送の仕事をしていた私にとって、社会福祉士の存在感は、徐々に大きなものになっていきました。そして、いつかは福祉の歴史や制度をじっくりと学ぶ機会を探していたこともあり、50歳を目前に控えた私は一念発起して、資格を取るため専門学校の門を叩きました。大学以来のレポート提出や障がい児をケアする実習に追われながらも、新入生として新鮮な日々を送りました。
学習を進める中で、魅力的なキーワードとの出会いもありました。困っている人を支援するために地域の社会資源をつなぐ「ソーシャルネットワーク」、必要な社会資源がない場合は政策すら自ら創造するために働きかける「ソーシャルアクション」。こうした言葉には、なにか正義の響きが感じられ、社会福祉士を目指したことは、私にとって必然だったのかもしれないと思えるようになっていきました。もし、社会福祉士の資格を取得せず、元NHKアナウンサーという肩書だけだったら、医療と福祉の専門職が連携する「もみじの家」に招かれることはなかったと思います。
ただ、学習を始めた当初から、資格をどう活かすか明確なイメージを持っていたわけではありません。せいぜい定年後に「福祉のおじさん」としてどこかに雇ってもらうためのアドバンテージになればいいな、という程度の目的でした。それが、想定外の転身を招くことになろうとは、本当に人生何が起きるかわからないと、つくづく感じております。
「もみじの家」の支援モデルを、全国に
30年間マスコミの人間として仕事をした後、53歳になる春に、私は「もみじの家」の初代ハウスマネージャーに就任する縁をいただきました。50歳を超えてから、まったく新しい世界に飛び込んだのは、もしかしたら「もみじの家」で正義を実行できるかもしれない、大きなことを言えば、「正義の味方」になりたいと思っているからなのかもしれません。
今も、昼夜を問わず、過酷なケアを続けている親御さんがいます。社会のサポートが行き届かず、子どもの将来の不安を消し去ることは難しいのが現実です。「もみじの家」は、そんなご家族の力になるために生まれました。
連日、休みなく続くお子さんの医療的ケアに追い詰められている人がいて、「もみじの家」を必要としていただけるのならば、私たちは全力でお役に立ちたいと思います。ゆったりと安心してくつろげる環境の中で、子どもたちには伸び伸びと過ごしてもらい、親御さんには明日への英気を養っていただくことが、私たちの使命です。ご家族の幸せのために、医療や介護、保育、ソーシャルワーカーなど、様々な分野のプロフェッショナルたちが力を合わせています。
短期的な目標は、足元をしっかりさせて、安定した施設運営を実現することですが、しかし、それで終わりではありません。「もみじの家」にいる時だけ、安心してくつろげればそれでよし、ではいけないのです。たとえ医療的ケアが必要でも、子ども同士の遊びや刺激による発達が促され、教育が保証され、就労への道が開けている。そんな社会にならなければ、本当の意味での安心とくつろぎは訪れません。
その実現のためには、重い病気や障がいのある子どもたちの成長を支えるためのネットワークが必要です。子どもを育む様々な専門職やボランティアが、制度の狭間で支援を受けられない子どもたちを常にサポートする。さらには、その狭間を埋めるような制度や政策を提言していく。「もみじの家」が、そのセーフティネットの中心的な役割を担う場所に進化することができれば、言うことはありません。
「もみじの家」は、まだ産声を上げたばかりですが、しっかりと独り立ちさせ、医療的ケアが必要な子どもとその家族が幸せを感じる場所が全国に飛び火するためのモデルとなれるよう、スタッフ一同、精一杯取り組んでおります。「もみじの家」と同じような機能を持った施設が各地に広がり、どこに住んでいても等しくケアが受けられる社会が実現する。そんな大きな夢を描きながら、第二の人生、全力を尽くす覚悟です。
皆様のご支援とご協力を、お願い申し上げます!